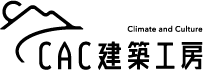Vol.27 例えばこんな続柄。奇妙で可笑しい家族譚3選
すっかり寒くなりましたね。みなさん、冬支度はできていますか? 僕はまだです。ライターのタラです。
11月と言えば、亡き母の誕生日です。ちなみに父と祖父が12月、祖母が1月、弟が10月、幼少の頃に病死してしまった一番下の弟が9月の生まれでした。つまり、9、10、11、12、1月と家族の誕生日が続いたのです。そして、何故か僕だけ4月生まれです。だからどうだという話ではありませんが、子供のころは不思議に思いました。
さて、今回は大好評の小説紹介第四弾です。選別テーマは「家族」。考えてみれば、誰しもが誰かの父であり、姉であり、息子であり、祖母であり、叔父であり妻であるわけで。そこには他人には分からない、家族ならでは物語があるのです。
では始めましょう。さてさて、最初のご家族は?

1『僕と妻の1778話』 眉村卓

<あらすじ>
余命一年と告げられた妻のために、自分には何ができるのか?
作家の夫が思いついたのは、一日一篇、物語を紡ぎ、妻に届けることだった。サラッと読めて、ほっこり笑える。そんな一篇である。
流石は作家とその妻。作品に制限を設けた。一つ、身内で楽しむだけでなく、対外的にも評価に耐えうるレベルであること。一つ、短編とはいえ、片手間では書けない「原稿用紙三枚以上」とすること。一つ、エッセイではなく、あくまで物語であること。一つ、病気や死、後味の悪い話や深刻過ぎる話題を扱わないこと。
一篇一篇積み重ね、やがて365日を越えて、1778日分、1778篇の物語となった。始まりの「詰碁」から「最終回」まで。厳選した52篇を収録した決定版。これが、約五年に及ぶ夫婦のあり方のリアル。
・・・・・・・・・・
とある統計によると、人間がもっともストレスを感じるのは「配偶者の死」だそう。分からなくもない。僕の祖父は、長年闘病していた祖母が亡くなった後、半年もしないうちに追いかけるよう亡くなりました。
さて、この話は実話である。実際に、作家・眉村卓氏は余命宣告を受けた妻のために一日一篇の物語を書き続けた。一日も欠かさずにである。そのおかげなのか、余命を大きく越えて妻は生き続けた。夫の小説を読むために頑張ったのかもしれないし、そうじゃないかもしれない。この話が美談でも美談じゃなくてもいい。ただ確実にいえるのは、この1778篇は夫婦の形であり、愛の記録である。こんな風に誰かを愛せるのは素敵だと思うわけで。
草彅剛・竹内結子のW主演で実写化もされている本作。映画独自の演出満載で、かなり小説とはまた違った味わいがあるとか。本書とあわせてオススメしておきます。
2『姉飼』 遠藤徹

<あらすじ>
はじめて「姉」を見かけたのは、村の繁栄を祝う祭りの縁日だった。出店にずらりと並ぶ、串刺しにされた姉たち。ぎゃあぎゃあ泣き喚き、鼻水や涎でぐしょぐしょになりながら、真っ黒な髪を振り乱す。異様な存在感に圧倒される少年。凍り付いたように体は動かず、思考は追い付かない。やがて父に「こんなもん、あんまり見ると目潰れんぞ」と促されて、無理やりその場を去ることになるのだが、その日から姉のことが頭から離れなかった。もう一度、姉らを見たい。それだけが少年の願いだった。
初めて姉を見てから十数年。ついに少年は自分の姉を手に入れる。夢にまで見た姉との甘美な生活。少年はすっかり虜になる。しかし、姉の寿命は短い。最初の姉を失った少年は、駆り立てられるように新しい姉を求めるのだが……。
・・・・・・・・・・・・
正直、ひと様におすすめできるような小説じゃないかもしれません。グロテスクすぎるカルトホラーです。ただ、世界観には引き込まれます。
あらすじで伝わるか微妙ですが、ここで言うところの「姉」とは、いわゆる兄弟姉妹の意味ではありません。恐らく、人間的なタブーの暗喩。一度手にすると、禁断症状的に欲することになる何か、だと思われます。
家族としての「姉」ではないので、ここで紹介するのはどうかなとも考えたのですが、まあ色々なジャンルの小説を取り上げたいという思いから、選んでしまいました。
読み手は選びます。無理な人は無理な話でしょう。好奇心旺盛かつ怖いもの見たさが刺激された方は是非! 異様な物語がクセになるかも……。
3『パパ・ユーア クレイジー』 W.サローヤン
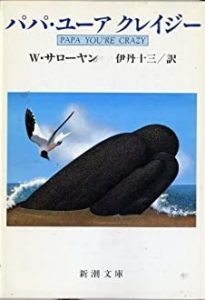
<あらすじ>
10歳の僕は、売れない物書きの父と海辺の家で暮らすことなった。父は、僕に、僕自身の小説を書くようにいう。僕自身って何だろう? 海や月や太陽や船は知っているけれど、自分自身や世界をほんとうに理解しているのだろうか。それは、小説を書きながら発見すればいいと、父はいうけれど……。
父は時に厳しく、時にユーモアたっぷりに、色々なことを教えてくれる。そこにはきっと生きる意味があるんだ。父と息子の、ちょっと風変りな二人暮らし。
アメリカの名匠が息子に捧げたといわれる、ハートウォーミングな詩的小説です。
映画監督としても有名な伊丹十三氏の翻訳が、いい味を醸しだしている必読の一冊。
・・・・・・・・・・・・
不思議な小説です。多分、買ったのは20代前半。その時は、全然楽しめず、途中で投げ出したのです。それから10年くらい放置し、ある時ふと読んでみようと思いました。すると何故かページを捲る手が止まらない。その10年で、僕は別に父になったわけではありません。それなのに、父と息子の話がスーッと入ってきたのです。
どこがどう面白いのか説明するのが難しいのですが、何でしょう、清々しいんです。これは読んでみないと、上手く伝わらない感情かもしれません。
みんな、誰かの子供です。だから共感できる何かがきっとあるはず。これは、文句なしにオススメの一冊です。

完全に趣味を生かした企画も、今回で第四弾。いかがでしたでしょうか?
ちょっと視点をずらして、家そのものから、そこに暮らす「人」にスポットを当ててみました(イレギュラーな作品も混じっていますが……)。
家族を大事に、と説教するつもりなどありません。が、かりにこの読書体験が家族をちょっと考えるきっかけにでもなれば、嬉しい限りです。
フランスの小説家、アンドレ・モーロワはこんな言葉を残しています。
「家族がなければ、人はこの世界でただ1人、寒さに震えるしかない」
お後がよろしいようで。